忘れたくない感覚〜時には昔に帰る〜
くれたけ心理相談室大阪支部 心理カウンセラーの宇野謙一です。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今では考えられないことかもしれませんが…。
親が子供の担任に「うちの子が言うことを聞かなかったら遠慮なくぶん殴ってください」と言う時代がありました。
外で悪いことをしたら、近所の大人がきちんと叱ってくれる時代がありました。
一人一人が、こうしたたくさんの周囲の本物の愛情で満たされている時代。
そんな時代が確かにあったと思うのです。
そうした背景の中で、子供も自分を振り返り、叱られたり殴られたりを真摯に受け止めていた気がします。
私も、そんな子供の一人でした。
その当時、テレビドラマで上司に殴られた部下が「(ご指導いただき)ありがとうございました」と頭を下げるシーンを何度か見かけ、愛情を持って部下に接し、身を持って指導する上司と、上司の思いを真摯に受け止め、反省と振り返りの姿勢を見せる部下、という関係性を非常にいいものだと思ったことが今も記憶に残っています。
今は、理由の是非を問わず、誰が誰に対しても手を上げるのは御法度の時代ですし、中学の教師をしている妹も、そうした背景があってか、揚げ足を取られたり指導がやりにくかったり、気苦労が絶えないようです。
ただ、もちろん暴力や暴言は、誰が誰に対しても許されることではありませんが、反面そうしたこともストローク(人が生きて行く上で精神的に必要不可欠な刺激)の一つとして作用することがあるとされています。
「ストローク」は人にとって心の栄養であり、誰でも快を感じる肯定的なストロークを欲し、得られないと飢えを感じるそうです。刺激への欲求(肯定的ストローク)が満たされないと精神的に支障をきたす恐怖に見舞われ、たとえば、殴られたり貶されたり叱られたりというような否定的ストロークでさえ手に入れようとします(決して否定的ストロークが欲しい訳ではなく、生命を維持するために「ストローク」そのものを求めているのです)。
そういう意味で、悪いことをしても叱られも殴られもしない、というのは、甘やかし以前に「ストローク」の欠落が心配される事態だと、一つの考え方として言えるでしょう。
たとえばですが…。
職場の管理職にもいろいろなタイプの方がおられます。
一口に(その方個人としては)仕事ができると言っても、度々正論過ぎる正論で追い詰め、朝令暮改があったとしても反論できないほど萎縮させ、本来の力が出せない状況に持ち込むようでは、部下の側から見ても、部下を育てるのに向いている立派な上司だとは言えない。と考えて差し支えないかと思います。
但し、言うことや指導内容が正当なものである以上、受け入れるところは受け入れなければならない。
そこに、「(ご指導いただき)ありがとうございました」と頭を下げる昭和のドラマの感覚が役立つような気がします。
相手の言動に問題があったとしても、その奥に「(部下育成以外の)正しい仕事のやり方」や「(間違っていると思える示し方であっても)その方なりの愛情」が感じられれば、「(ご指導いただき)ありがとうございました」という気持ちで受け入れる。そういう考え方もあっていいと思うのです。
私が、もし、そういう状況に陥ったとしたら、不快な気持ちには目を瞑って「(ご指導いただき)ありがとうございました」という気持ちで相対するのもいいかもしれないなと、最近思うようになりました。
今は、暴力にせよ、暴言にせよ、限度や加減を弁えず、過剰に過ぎる事象が多いため、難しい点も多々あることとは思いますが、時には、昭和のドラマの感覚で人間関係を見つめ直してみるのもいいかもしれない。
そういう考え方もあっていいと思います。
「(ご指導いただき)ありがとうございました」と言える真摯な姿勢は、「痛みを知る『傲慢さのない人間』」にもつながる。そう信じています。
お楽しみ様でした。

親が子供の担任に「うちの子が言うことを聞かなかったら遠慮なくぶん殴ってください」と言う時代。外で悪いことをしたら、近所の大人がきちんと叱ってくれる時代。そうした背景の中で、子供も自分を振り返り、叱られたり殴られたりを真摯に受け止めていた気がします。時には、昭和のドラマの感覚で、何があっても、不快な気持ちには目を瞑って「(ご指導いただき)ありがとうございました」という気持ちで相対するのもいいかもしれないですね。
投稿者プロフィール
- くれたけ心理相談室(大阪支部)心理カウンセラー
-
くれたけ心理相談室(大阪支部)は、大阪府大阪市・八尾市を拠点に心理カウンセリングを承っております。エリア外の皆様にも、Zoomや電話等によるカウンセリングにて対応させていただいております。
カウンセリングを通じて、「困っていた問題」 が 「新たな気づきや成長へのきっかけ」となることを心から願っています。
最新の記事
 今、思うこと2025年12月31日今年最後のご挨拶~強くあるために~
今、思うこと2025年12月31日今年最後のご挨拶~強くあるために~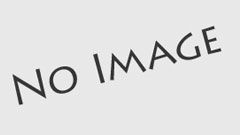 今、思うこと2025年12月30日不器用な愛~殿下とライオン~
今、思うこと2025年12月30日不器用な愛~殿下とライオン~ 今、思うこと2025年12月29日ロジカルハラスメント~時に正論は無理解な暴力~
今、思うこと2025年12月29日ロジカルハラスメント~時に正論は無理解な暴力~ 今、思うこと2025年12月28日厳しい態度に耐えられない~自身の甘えを排除する~
今、思うこと2025年12月28日厳しい態度に耐えられない~自身の甘えを排除する~


